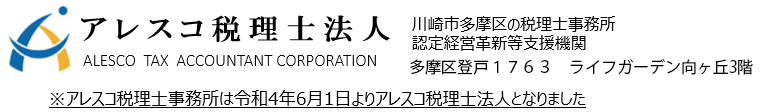相続対策の基本は3本柱!「節税・分割・納税」から考える税理士法人の支援
相続対策と聞くと、「税金をできるだけ少なくしたい」というイメージを持たれる方が多いかもしれません。しかし、実際の相続では「節税」だけでなく、「円満な分割」や「スムーズな納税」も極めて重要な視点となります。
税理士法人として私たちは、これら3つの観点から総合的な相続対策をサポートしています。以下、それぞれの観点からの対策をご紹介します。
1. 節税対策:早めの生前対策が鍵
相続税の負担を軽減するためには、生前からの準備が欠かせません。主な節税策は以下の通りです。
- 基礎控除の活用
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。相続人を増やすことで控除額も大きくなります。 - 生前贈与の活用
年間110万円までの贈与は非課税です。長期的に計画的な贈与を行えば、相続財産そのものを減らすことができます。 - 不動産の活用
土地や賃貸物件などは、評価額が現金より低くなる傾向があり、節税につながります。特に「小規模宅地等の特例」は自宅や事業用地について大幅な評価減が可能です。
税理士としては、相続財産の内容・構成に応じて、最適な節税プランをご提案します。
2. 分割対策:トラブルを避けるための仕組みづくり
相続税がかからないケースでも、遺産分割でもめることは少なくありません。特に、不動産が財産の大半を占める場合、分けにくさが原因で相続人同士の関係が悪化することもあります。
- 遺言書の作成
被相続人の意思を明確に伝えるため、遺言書はとても有効です。公正証書遺言であれば法的効力も高く、安全です。 - 家族会議の実施
相続が「争族」にならないよう、生前に家族間で話し合う場を設けることも大切です。税理士として、家族会議のファシリテートも行います。 - 代償分割の検討
現物で分けられない財産(例:自宅)を相続する人が他の相続人に現金等を支払う「代償分割」も一つの選択肢です。
3. 納税対策:スムーズな納税でトラブル回避
相続税は原則、現金で一括納付が求められます。しかし、遺産が不動産中心で現金が少ない場合、納税資金に困るケースが多くあります。
- 生命保険の活用
死亡保険金は「500万円×法定相続人の数」まで非課税で受け取ることができ、納税資金の確保手段として有効です。 - 納税方法の検討
現金での納付が困難な場合、「延納」や「物納」などの制度もあります。税理士はこれらの申請手続きやシミュレーションも支援します。 - 事前評価による納税額の把握
あらかじめ相続税額の目安を把握することで、納税準備を早めに行うことが可能です。生前の財産評価は非常に重要です。
まとめ:総合的な対策が円満な相続への第一歩
相続対策は「節税」だけでなく、「争いを避ける分割対策」や「確実に納税するための準備」まで一体で考えることが不可欠です。
私たち税理士法人では、お客様のご家族構成や財産状況に応じて、オーダーメイドで相続対策をご提案しています。ご相談は初回無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。