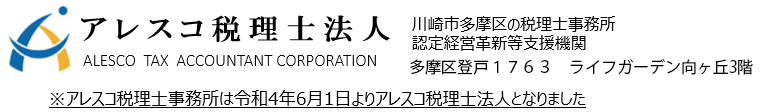外国税額控除の基本と各国の制度の違いについて
海外でビジネスを行う企業にとって、「外国税額控除」は非常に重要な制度です。これは、日本企業が海外で得た所得に対して現地国で課税された場合に、同じ所得に対する日本での法人税の二重課税を防ぐための制度です。
たとえば、日本の企業がタイで得た所得に対してタイ政府から源泉徴収された場合、同じ所得に対して日本でも法人税が課されることになります。このとき、外国で支払った税金分を日本での法人税額から控除できるのが「外国税額控除」です。
外国税額控除の基本的な仕組み
日本では、控除限度額の計算により、控除できる金額が制限されます。限度額の算出式は以下の通りです:
控除限度額 = 日本の法人税額 ×(国外所得 ÷ 全世界所得)
つまり、外国で支払った税額すべてが控除できるわけではなく、日本の税率と比べて現地の税率が高すぎる場合には、一部の外国税が控除しきれず、実質的に二重課税となるケースもあります。
この控除限度額を超える税額については、一定の条件下で翌年度以降への繰越しや、過去年度への繰戻しが可能です(法人税法上は原則1年間の繰戻しと3年間の繰越しが可能)。
各国の考え方の違い(「クレジット方式」と「エクゼンプション方式」)
外国税額控除の考え方は、各国で異なりますが、大きく分けて次の2つの制度に分類されます。
① クレジット方式(Credit Method)
これは日本をはじめ、アメリカ、イギリスなど多くの国が採用している方式です。
国外所得を自国の課税所得に含めたうえで、外国で課された税額を自国の税額から控除するという考え方です。
メリットは、課税の公平性を維持できる点で、企業がどこで活動しても国内と同水準の税負担となるよう調整できます。一方で、控除限度額の計算や申告が煩雑になりやすいのがデメリットです。
② エクゼンプション方式(Exemption Method)
これは、フランス、オランダ、シンガポールなど一部の国が採用している方式で、国外所得を**自国の課税所得に含めない(非課税とする)**ことで、そもそも二重課税を避ける方法です。
非常にシンプルな制度で、申告も簡素化されますが、場合によっては租税回避の温床となり得るため、適用対象は限定的なことが多く、特定の所得(配当・譲渡益等)に限られています。
まとめ
日本の企業が海外で事業を行う場合、どの国で、どの税率で課税され、そして日本でどのような扱いになるかを理解することが極めて重要です。とくに進出国によっては、日本と制度が大きく異なるため、事前の調査と設計が欠かせません。
外国税額控除はあくまで「税額控除」であり、控除しきれない場合には実質的に損をすることにもなり得ます。企業としては、国際税務の専門家と連携しつつ、進出国の税制、日本の控除制度の両面から最適な対応を検討することが求められます。