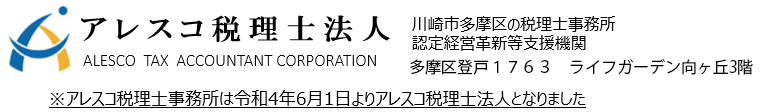移転価格税制とは?―算定方法と文書化ルールの基本を解説
グローバルに展開する企業にとって避けて通れないのが「移転価格税制」です。
これは、**多国籍企業グループ内の取引価格(移転価格)**が市場の通常の価格から不当に乖離していた場合、税務当局がその価格を否認し、課税所得を修正できる制度です。
本記事では、移転価格の算定方法と、企業に義務付けられている文書化(ドキュメント)対応について解説します。
なぜ移転価格税制が必要なのか?
企業グループが国境を越えて取引する場合、税率の低い国に利益を多く残すように意図的に取引価格を操作すると、課税所得が適正に計算されないリスクが生じます。こうした「税源の移転」を防止するために、各国では移転価格税制を整備しています。
税務当局は、グループ内取引が「**独立企業間価格(arm’s length price)」で行われているかどうかを確認し、そうでなければ適正価格に基づいて所得を修正します。
移転価格の算定方法(主要な5方式)
独立企業間価格は、独立した第三者間で同様の条件下で行われたであろう価格を基準とします。OECDや日本の税制上では、以下の5つの代表的な方式が認められています。
1. 独立価格比較法(CUP法)
比較対象となる同種の取引の市場価格と、自社のグループ内取引の価格を比較して妥当性を判断する方法。
最も直接的な方法ですが、正確な比較対象が得にくいのが難点です。
2. 再販売価格基準法(RP法)
グループ会社が仕入れた商品を第三者に販売する際の販売価格から適正な利益を控除して、仕入価格の妥当性を評価する方法。
流通業などに適しています。
3. 原価基準法(CP法)
製造原価などのコストに通常の利益率を加算して販売価格の妥当性を判定する方法。製造業に多く使われます。
4. 取引単位営業利益法(TNMM)
グループ会社と第三者との営業利益率を比較して、価格の妥当性を判断する方法。比較可能な企業情報があれば、汎用性が高く実務上よく用いられます。
5. 利益分割法(PS法)
グループ企業が共同で価値を生み出すような取引(例:共同研究開発)の場合に、利益を合理的に分割する方法。複雑な構造の取引に適用されます。
文書化の義務と3層構造(マスターファイル・ローカルファイル・CbCR)
OECDが推進する「BEPS行動計画13」に基づき、多国籍企業には移転価格に関する情報開示(文書化)義務が課されており、日本でも平成28年から次の3層構造による文書化が導入されています。
① マスターファイル(Master File)
企業グループ全体のビジネス概要、組織構造、無形資産、財務状況などを記載する文書。売上高1000億円以上の企業グループに義務があります。
② ローカルファイル(Local File)
日本法人と海外関連者との取引に関する価格設定方法の妥当性を説明する文書で、移転価格税制の適用対象となる法人においては原則として作成義務があります。税務調査時に提出を求められる可能性が高い重要文書です。
③ 国別報告書(CbCR:Country-by-Country Reporting)
グローバル全体の所得・税金・事業活動状況を国別にまとめた報告書で、連結売上高750億円超の企業グループに義務があります。電子的に国税庁に提出します。
文書作成のポイントと経営者の留意点
移転価格に関する文書は、形式的に整っていても内容が曖昧であれば否認されるリスクがあります。特にローカルファイルについては、「比較対象の選定理由」や「価格決定プロセスの正当性」を明確に記載する必要があります。
経営者としては、以下の点を意識することが重要です:
- 海外関連者との取引金額が一定額を超える場合、毎期ローカルファイルの作成体制を整備しておく
- 海外子会社の事業内容や利益率などを常にモニタリングし、価格設定に一貫性を持たせる
- 必要に応じて、移転価格文書の外部作成やレビューを専門家に依頼する
まとめ
移転価格税制は、単なる税務リスク対策にとどまらず、グループ全体の経営と税務を整合的に運営するための重要な制度です。
文書化義務や税務調査への対応など、経営者自身が制度の基本を理解し、実務上のリスクを予防する体制を整えることが、国際展開における競争力にもつながります。