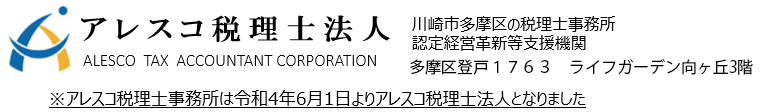民法で押さえておくべき相続の基本知識9選|税理士法人がやさしく解説
相続税申告に関する手続きは税法だけでなく、「民法」の知識も不可欠です。民法に基づく相続人や相続財産の確定、分割方法によって、最終的な相続税の申告内容が大きく変わることもあります。
ここでは、相続においてよく登場する民法の重要な概念を、税理士法人の視点でわかりやすく解説します。
1. 寄与分とは?
「寄与分」とは、被相続人(亡くなった方)の財産の維持・増加に特別な貢献をした法定相続人に対し、その分を相続分に加算する制度です。
たとえば、長年介護をしてきた子や家業を支えてきた相続人が対象になり、他の相続人と公平を図るために活用されます。
2. 特別受益とは?
「特別受益」とは、生前贈与や結婚・住宅取得時の援助など、被相続人から特別に財産を受けていた相続人がいた場合に、それを遺産の前渡しとみなして、相続分から差し引く考え方です。
寄与分とは逆に、特別な利益を既に受けていた分を考慮して、他の相続人とのバランスを取ります。
3. 代襲相続とは?
「代襲相続」は、本来相続人になるはずの人(例:子)が、相続開始前に死亡している場合、その子(孫など)が代わりに相続する制度です。
特に相続順位が高い直系卑属に多く見られ、二次的な相続関係に注意が必要です。
4. 非嫡出子(非摘出子)とは?
「非嫡出子」とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を指します。以前は法定相続分が嫡出子の半分とされていましたが、平成25年の最高裁判決以降は、嫡出子と同等の相続分を持つようになりました。
5. 養子(普通養子と特別養子)の違い
- 普通養子:実親との親子関係も残るため、両方から相続できます。相続税の法定相続人にも含まれます(最大2人まで基礎控除対象に)。
- 特別養子:裁判所の手続きを経て実親との関係を完全に断ち、養親とのみ親子関係を持ちます。原則6歳未満の子が対象です。
相続税の基礎控除額や相続人の数に直結するため、申告時は区別が重要です。
6. 遺言とは?
「遺言」は、被相続人が生前に自分の死後の財産分けや意思を明示する法的文書です。
形式には以下の種類があります:
- 自筆証書遺言:本人が全文を手書き。法務局での保管制度あり。
- 公正証書遺言:公証役場で作成。最も確実。
- 秘密証書遺言:内容を秘密にしつつ形式を整える。
遺言があることで遺産分割協議を省略できる場合もあります。
7. 死因贈与とは?
「死因贈与」は、贈与者が死亡することを条件に財産を譲る契約です。
遺言と似ていますが、契約であるため、受贈者の同意が必要です。相続税の課税対象となり、遺贈と同様の扱いを受けます。
8. 遺産分割協議とは?
複数の相続人がいる場合、誰がどの財産を相続するかを決める話し合いを「遺産分割協議」といいます。
- 全相続人の合意が必要
- 書面化(遺産分割協議書)が原則
- 税務署への相続税申告時に必要な書類になることも
不動産登記や預金の解約などでも協議書の提出が求められます。
9. 代償分割と換価分割とは?
- 代償分割:不動産などを一人が相続し、その代わりに他の相続人に現金を支払う方法。相続税の納税計画に合わせて選ばれることも。
- 換価分割:不動産や株式などを売却して現金化し、それを相続人で分ける方法。現物分割が困難な場合に有効です。
それぞれ、課税上の影響(譲渡所得課税など)にも注意が必要です。
まとめ:民法の理解が、相続税対策にもつながります
税理士法人として相続税の申告や対策を行う際、これら民法の知識が土台となります。円滑な遺産分割・節税・申告のためには、相続人ご本人やご家族にも基本的な知識が必要です。
当法人では、民法の仕組みを踏まえた相続設計や、生前対策、遺言作成支援、遺産分割協議書の作成支援まで一貫して対応しております。お気軽にご相談ください。